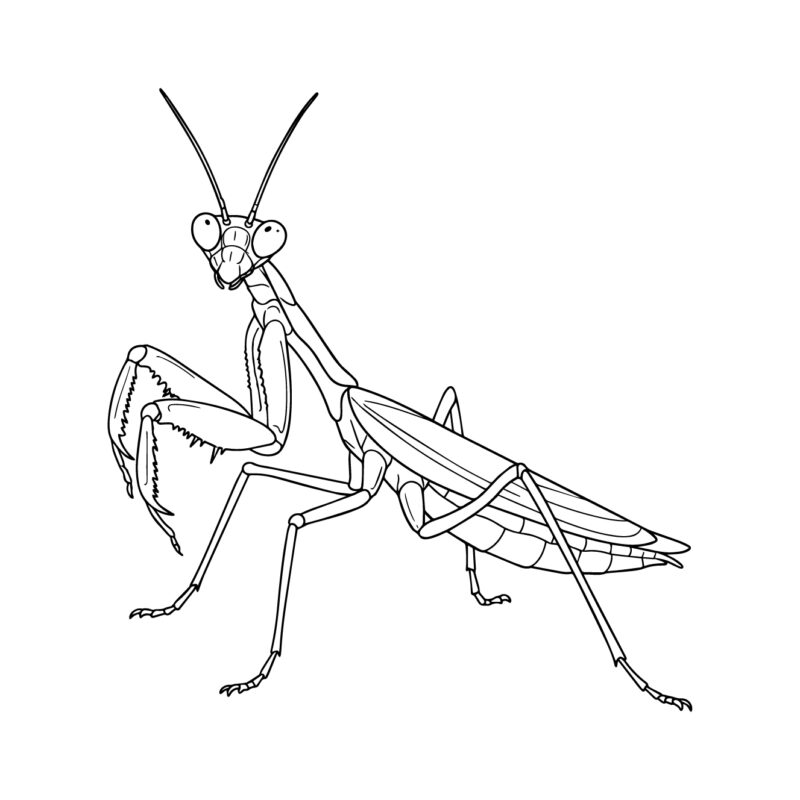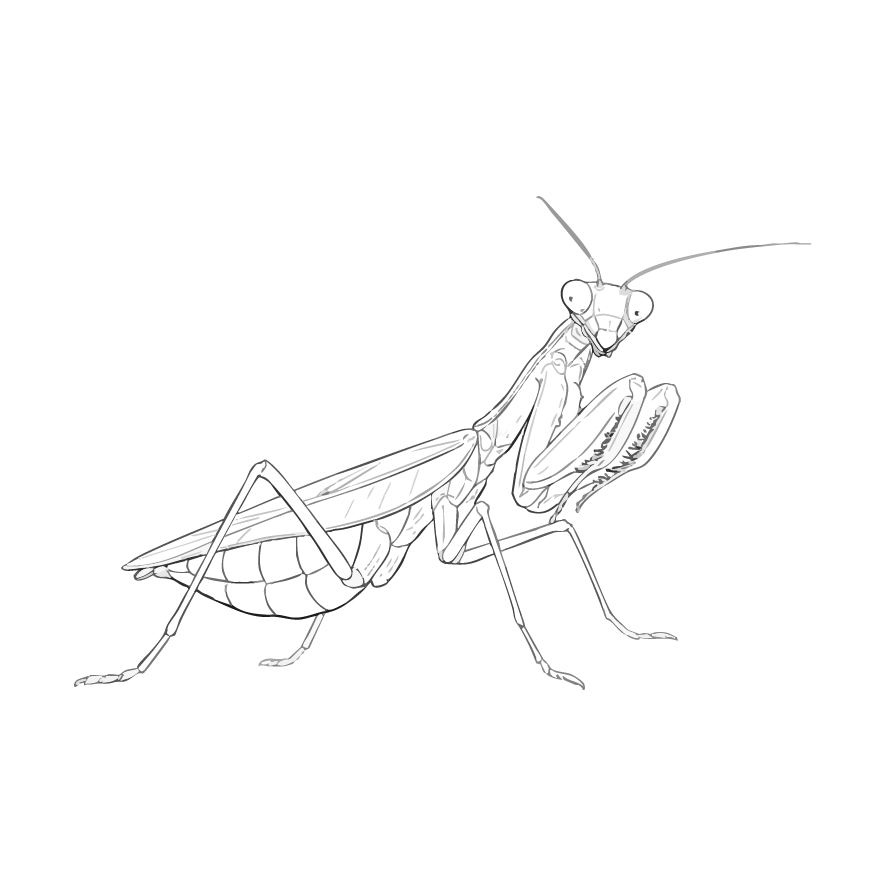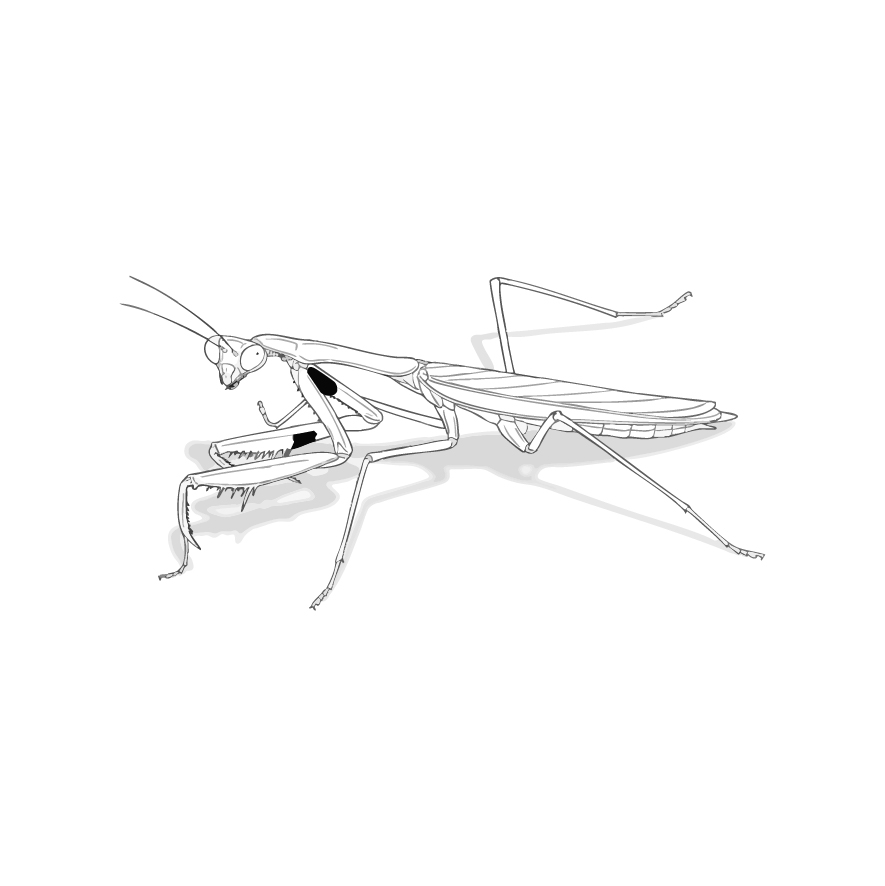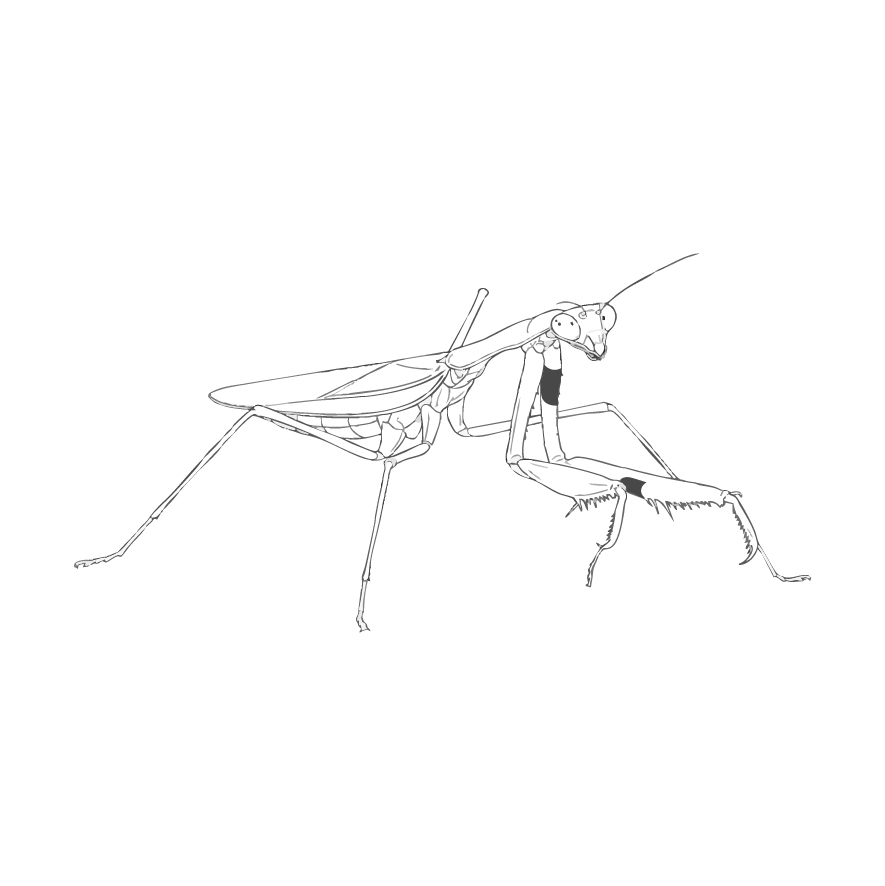コカマキリの塗り絵
難易度:
 ~
~

 ~
~

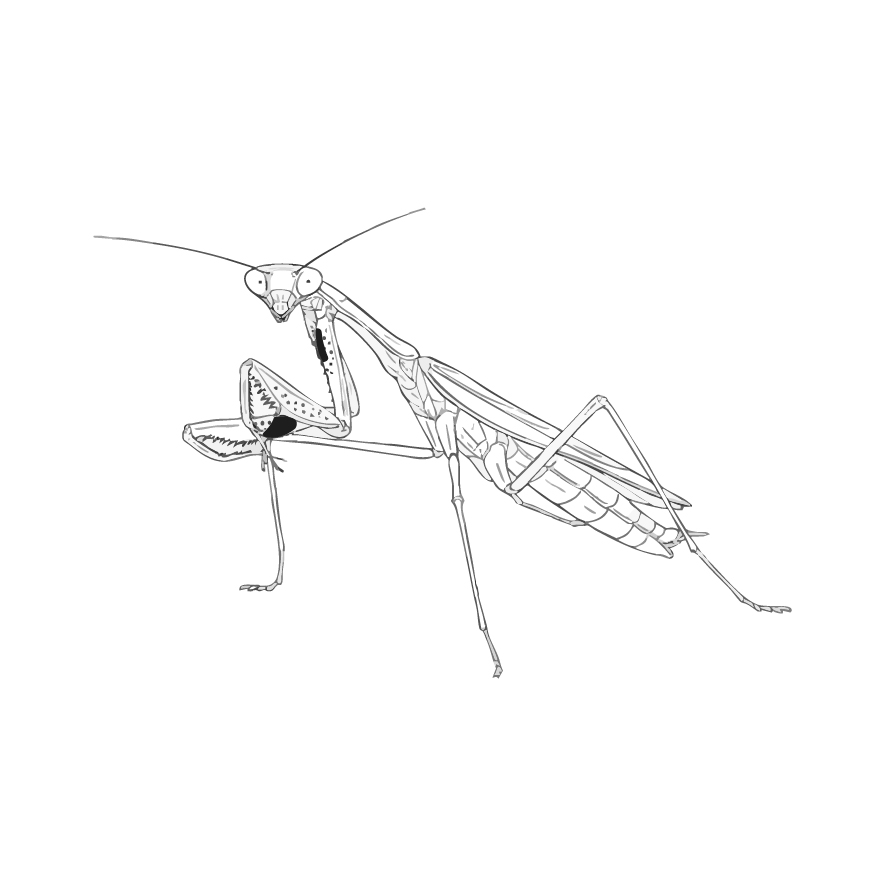
コカマキリの特徴
日本の田んぼや草原に住む!小さな狩人
コカマキリは、カマキリの仲間のうち、日本の身近な場所に広く生息する種類です。名前の通り、他の大きなカマキリと比べて体が小さく、体つきががっしりとしているのが特徴です。草原や畑などで、小さな虫を捕まえて暮らしています。
名前と見た目の由来
- コカマキリ:体のサイズが、大型のオオカマキリなどに比べて「小さい」ことから名付けられました。
- 英語名:英語では「Small Mantis(スモール・マンティス)」のように呼ばれることがあります。
- カマ:前足が、獲物を捕まえるのに適したカマのような形をしていることから、カマキリの仲間全体がこの名前で呼ばれています。
小さくて がっしりした 姿
コカマキリは、その小ささと体つきに特徴があります。
- 大きさ:体長はだいたい3センチメートルから5センチメートルくらいで、人差し指くらいの長さです。
- 体つき:オオカマキリのようなスマートな体つきではなく、ずんぐりとして、がっしりしています。
- 色:体全体の色は、緑色のものと茶色(褐色)のものがあり、生息している環境によって色が違います。
- 胸の紋:胸のあたりには、白い点のような紋があるのが特徴です。
普段は草や枝の上にじっと隠れていますが、獲物を見つけると、カマのような前足を素早く動かして捕まえます。
どこに 住んでいるの?
コカマキリは、日本全国のさまざまな場所に広く生息しています。
- 主な生息地:本州、四国、九州などに広く分布しています。
- 生息する場所:日当たりの良い草原、河原の草むら、田んぼのあぜ道、畑など、草がたくさん生えている場所に多く見られます。
小型なため、大人の目の高さより低い、地面に近い草むらに隠れていることが多いです。
どんなものを 食べているの?
コカマキリは、肉食の昆虫です。
- 成虫・幼虫:主にバッタ、コオロギ、ハエなどの小さな虫を捕まえて食べます。カマのような前足で獲物をしっかりとつかみ、逃がしません。
- 卵:メスは秋に、「卵鞘」と呼ばれる、泡のようなもので包まれた卵を、草の茎や枝などに産み付けます。卵鞘は冬の寒さから卵を守る役割をしています。
コカマキリの色を塗るコツ
色の選び方:自然に溶け込む「保護色」を表現しよう!
コカマキリは、緑色と茶色の二つのタイプがあり、隠れるのが得意な色をしています。どちらのタイプを塗るか決めて、自然に溶け込むような色を表現しましょう。
- 緑色のタイプ:全体を鮮やかな緑色ではなく、黄緑色や少し茶色がかった緑色で塗ると、草の間にいるような自然な色になります。
- 茶色のタイプ:薄い茶色や枯れた草のような色をベースに、濃い茶色を混ぜて塗ると、土や枯れ葉に隠れている感じが出ます。
- 紋:胸のところにある白い点のような紋は、真っ白で小さく描くと、チャームポイントになります。
- カマの色:獲物を捕まえるカマは、体の色と同じですが、先端やギザギザした部分に濃い色で影をつけると、鋭さが表現できます。
塗り方:がっしりした体つきを表現しよう!
コカマキリの小さな体と、力強い前足を意識して、立体感が出るように塗りましょう。
- 立体感:丸くてがっしりした胴体や、力こぶのように見えるカマのふくらみの部分に、明るい色を塗り、その周りの影になる部分に濃い色を塗ると、筋肉質な立体感が出ます。
- 目のツヤ:大きな目玉は、黒や濃い茶色で塗り、光が当たったような白い点を一つ入れると、生き生きとした表情になります。
- 翅の質感:翅は、薄い茶色やごく薄い緑色で、向こう側が透けて見えるようなイメージで軽く塗ると、薄い質感が表現できます。
ぬりえを楽しむためのヒント!
- 自由に表現しよう!
- 背景にバッタや小さな虫を描き足して、コカマキリが獲物を狙っている様子を表現しても楽しいね。自由に表現しよう!
- 生息地を描き足そう!
- コカマキリが隠れている草むらを、色々な種類の緑色で描き足すと、絵がもっと生き生きするよ!
-
コカマキリ オス

-
コカマキリ オス2

-
-
コカマキリ メス

-
コカマキリ メス2

-