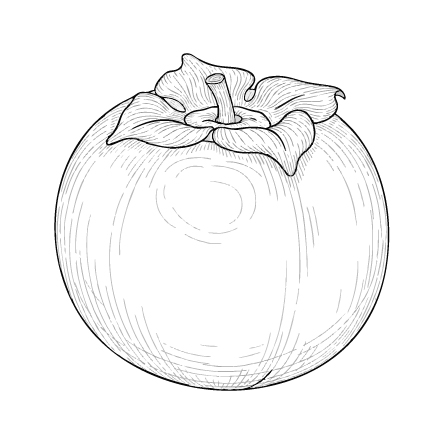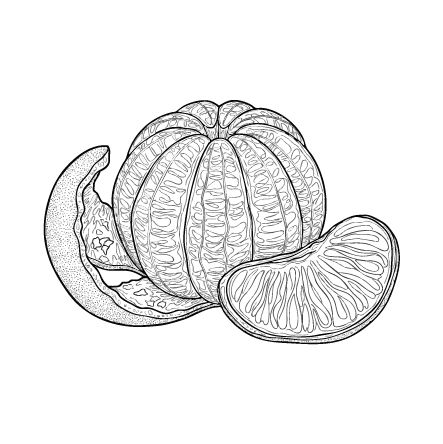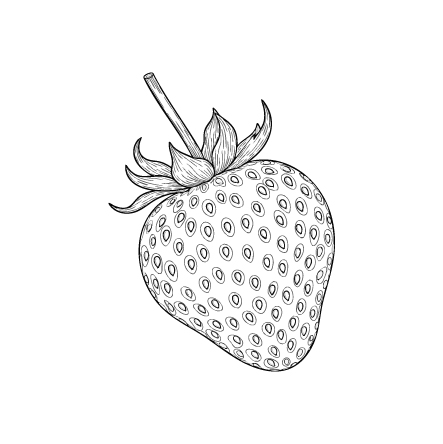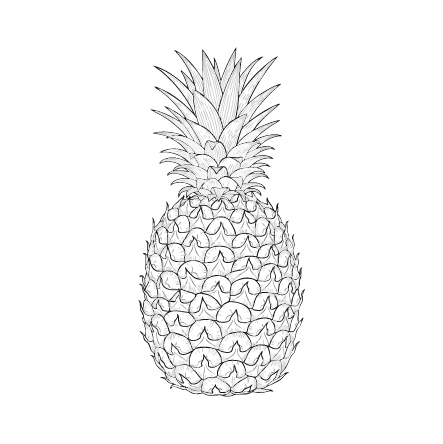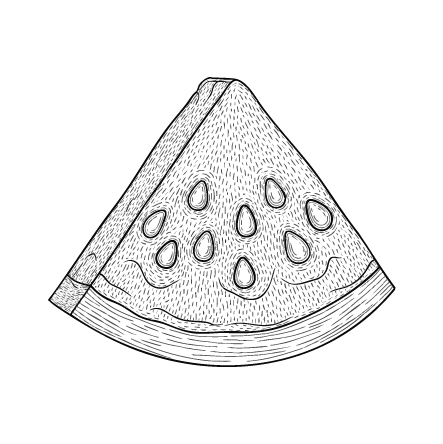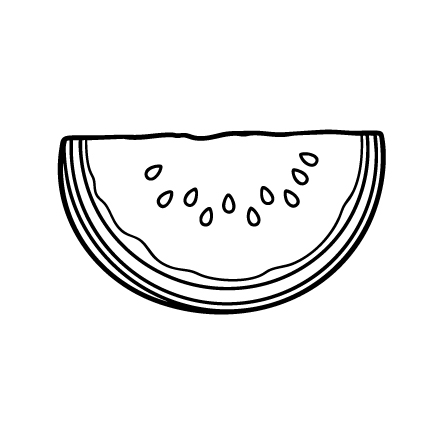スイカの塗り絵
 ~
~

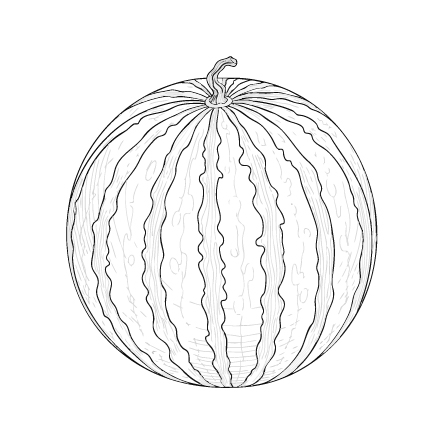
スイカの特徴
大きくて丸い! 夏の王様 スイカ!
スイカは、大きくて丸い形と、緑色と黒色の縞模様が特徴的な果物です。真っ赤な果肉は甘くて、水分がたっぷりなので、暑い夏に食べると、とても美味しくて涼しい気持ちになります。「夏の王様」とも呼ばれ、みんなに人気があります。
スイカの起源
スイカは、今から4,000年以上前に、アフリカ大陸の乾燥した場所で生まれたと言われています。古代エジプトでは、すでに栽培されていて、壁画にも描かれています。水分が豊富なので、砂漠を旅する人たちの、大切な飲み物でした。その後、シルクロードを通ってアジアに伝わり、日本には、中国からおよそ300年ほど前に伝わったと言われています。
どんなところにできるの?
スイカは、温かくて太陽の光をたくさん浴びる地域で育ちます。地面に這うようにして育ち、つるの先に大きな実をつけます。日本では、夏になるとたくさんのスイカが作られます。鳥や動物に食べられないように、畑で大切に育てられています。
スイカができるまで
スイカは、春から夏にかけて、黄色い小さな花を咲かせます。この花が、ミツバチなどの昆虫によって受粉すると、だんだんと膨らんで、スイカの実に変わっていきます。最初はとても小さな緑色の実ですが、太陽の光をたくさん浴びて、だんだんと大きくなり、美味しそうな縞模様が出てきます。
スイカの色々な種類
スイカには、色々な種類があります。
- 大玉スイカ:一番一般的なスイカで、大きくて重いです。
- 小玉スイカ:小さいスイカで、冷蔵庫にも入れやすく、食べきりやすいので人気があります。
- 黄色いスイカ:果肉が黄色い珍しいスイカです。甘みが強いのが特徴です。
- 種無しスイカ:種がほとんどないスイカで、とても食べやすいです。
- 四角いスイカ:四角い入れ物に入れて育てる、珍しいスイカです。プレゼントなどに使われます。
- 黒いスイカ:真っ黒な皮のスイカで、とても珍しい高級品です。
栄養満点!
スイカには、体に良い栄養がたくさん入っています。
- 水分:スイカのほとんどは水分なので、熱中症の予防にとても役立ちます。
- カリウム:体の中のいらないものを出して、血圧を下げるのを助けるカリウムが豊富です。
- シトルリン:スイカにしか含まれていない特別な成分で、血の流れを良くしたり、体を元気にする働きがあります。
スイカの色を塗るコツ
色の選び方:夏の涼しさを表現しよう!
スイカのぬりえでは、その美味しそうな色と、涼しい雰囲気を表現することがポイントです。緑色や赤色、そして黒を使いながら、光が当たっているところや、影になっているところを工夫して塗ると、もっと本物らしくなります。
- スイカの皮の色:
- 緑色と黒色の縞模様:緑色の部分と、黒色の部分を丁寧に塗り分けましょう。緑色に少しだけ濃い緑色や茶色を混ぜて塗ると、本物らしい深みが出ます。
- 光が当たっているところは、少しだけ薄い緑色を残しておきましょう。
- スイカの果肉の色:
- 真っ赤な果肉は、赤色で塗ります。少しだけピンク色やオレンジ色を混ぜて塗ると、美味しそうな感じが出ます。
- 果肉の白い部分は、白で残しておきます。
- 種の黒色:
- 種は、黒色で、少し大きめに描き加えましょう。
- 背景の色:
- スイカは、夏に食べることが多いので、背景は青い空や太陽などを描き加えて、夏らしい雰囲気を表現してみましょう。
立体感を出す塗り方:「濃淡」と「影」を意識しよう!
スイカの形は、丸くて大きいです。この「濃淡」と「影」を上手に表現すると、ぬりえがもっと生き生きして見えます。
- 濃淡を出す場所:
- スイカの丸い部分に、光が当たっているところを想像して、少し薄い色を残しておきましょう。
- 影を出す場所:
- スイカの下の部分や、地面に接しているところは、影になります。
- こういったところに、濃い緑色や黒色を塗ると、スイカがもっこりした立体的な感じになります。
絵の具や色鉛筆、画材のコツ!
- 色鉛筆:
- 力を入れて濃く塗ったり、力を抜いて薄く塗ったりすることで、濃淡を表現しやすいです。
- 緑色の上に、他の色(黒や茶色など)を重ねて塗ると、深みのある色になります。
- クレヨン:
- クレヨンで塗ると、つるつるした感じを出しやすいです。指でこすって色をぼかすこともできます。
- 絵の具:
- 緑色に少しだけ水を混ぜて、薄い緑色を作り、光が当たっている部分に塗ってみましょう。乾いてから、もう一度濃い緑色を重ねて塗ると、深みが出ます。
きみの想像力と、自由な発想で、世界に一つだけの素敵なスイカのぬりえを完成させてください!
-
スイカ

-
スイカ2

-
-
スイカ3

-